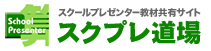サービス終了のお知らせ
小6算数 小6算数の教材です
小6算数 複合立体の体積
立体の体積の教材です。統合的な考えをねらって、5年生で分割して求めた複合立体の求積を、底面積×高さで求めることができることに気付かせます。立体を回転させるアイディアに気付いた子が出たら、立体を回転させる図をコマ送りで提示し、共有させていきます。1頁目はブロックを分割して動かすことができ、6頁目は底面積が見えるように半透明の図を提示できるようにしました。 Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます) https://jamboard.google.com/d/1OyGZmPDKhSLz8TxRXyJRMFawZrsAuKeq-GXXS4m9lSc/ed...
小6算数 比例の活用
6年生「比例の活用」の授業で使用した教材です。Aさん、Bさんをそれぞれアニメーション表示して、Bさんの方が速いことに気付かせ、「同時にスタートしたら?」と問います。アニメーション表示させると、「追いつきそう‥一周遅れになる‥」などの声が出るので、「何分後に?」を問います。一周の時間や道のり(条件)を教えてほしいという声を引き出して、Aさん3分、Bさん2分、1周600mの条件で、解いていきます。これまでに学習した、比例の式、比例の表、比例のグラフを活用しながら、子どもたちは問題解決に向かいました。ボタンなどをクリックすることで、様々なアニメーションが再現されます。ボタンによってはストップも...
小6算数 10進法を使った時計
「量と単位」の発展教材です。フランス革命の時に取り入れらたれという数学史を基に教材化しました。10進法だけで表した時刻が、一般的な時計だと何時何分になるのか考えさせます。時計の長針と短針は、CTRLキーを押しながらドラッグすると、動かすことができます。 参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小6算数 ナンバープレートでメイク10
ナンバープレートを使ってメイク10をする教材です。スロットマシーン提示で「2334」などの数値を順番に提示することができます。どの数値も商分数を使って解くことができるので、6年生で扱うと多様な数の見方を引き出すことができます。
小6算数 片手だけでいくつまで数えられるかな?
10進法と2進法の違いを扱った教材です。片手だけでいくつまで数えられるか考えさせた後、31まで数えることができることを伝えると、「どうやるの?」と興味をもちます。画面を次々に送っていくと、1から31までのやり方が分かります。なお、始めの頁は、指をクリックすると、折れたりり戻ったりするように設定してあります。
小6算数 資料の整理(スロットマシン提示)2
資料の整理の教材です。こちらはBの方です。Aと合わせて、サンプル画面のように提示して使います。スロットマシンで提示された分だけ割引券をもらえると場面です。AもBもどちらも同じ平均ですが、最大値や最小値、中央値などが違います。とぢらを引きたいか決めることで、資料の代表値として平均以外の見方を引き出します。加固希支男先生の実践を参考にしました。 Aの方:http://www.schoolpresenter.jp/projects/318 参照http://blogs.yahoo.co.jp/jyugyoken/62295534.html
小6算数 資料の整理(スロットマシン提示)
資料の整理の教材です。スロットマシンで提示された分だけ割引券をもらえると場面です。AもBもどちらも同じ平均ですが、最大値や最小値、中央値などが違います。とぢらを引きたいか決めることで、資料の代表値として平均以外の見方を引き出します。加固希支男先生の実践を参考にしました。参照http://blogs.yahoo.co.jp/jyugyoken/62295534.html
小6算数 継子立て
塵劫記の「継子立て」を教材化したものです。ICTを使うことで、ルールの確認と違う枚数の場合を容易に提示できます。また、頁保存を使うことで、残った数字カードがいつも2の累乗になることに気付かせることもできます。数字カードはDelキーか削除ボタンを使って消します。
小6算数 校舎の高さは?
拡大図・縮図の教材です。塵劫記の「立木の長をつもる事」を素材に、三角定規を使って校舎の高さを測る場面を問題にしました。三角定規の直角二等辺三角形を使うと高さが分かることを視覚的に理解できるようにしています。参照http://blogs.yahoo.co.jp/jyugyoken/62295534.html
小6算数 1つの点を中心とした拡大図
1つの点を中心として、三角形を2倍に拡大することを学ぶ教材です。頂点だけでなく、辺上の点、三角形の内部の点、三角形の外部の点を中心とした2倍の拡大図をアニメーションでイメージすることができます。中学校で学習する任意の点を中心とした拡大図の素地を育てることをねらいました。