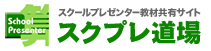サービス終了のお知らせ
新着の教材 新しくアップロードされた教材です
小3算数 ヘキソミノ(緑表紙)
緑表紙(3年上)の問題をスクプレで教材化したものです。まずは6つに切って丸の数か同じになるように取り組ませた後、「全部形を変えて」という文を提示します。ヘキソミノ(6つの正方形を辺に沿ってつなげた形)を作る教材に発展させます。丸をクリックした後、下の色パレットをクリックすると着色できるように設定しました。 参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小4算数 長方形を正方形に(裁ち合わせ)
和算の「裁ち合わせ」を教材化したものです。長方形を一度だけで切って正方形にします。簡単な数値のものを3つ取り上げました。「同じようにできる長方形が他にもあるかも?」という問いを引き出し、自分で長方形を探す活動まで想定して作りました。参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小5算数 単位分数スロット
異分母分数のひき算の発展教材です。分子が1で分母の数字が連続する分数の引き算のきまりを教材化したものです。スロットをクリックすると、1/3-1/4のような数値を設定することができます。通分しなくてもぱっと計算ができることに気付く子を引き出していきます。 参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小5算数 分母の違う分数
同値分数の教材です。少しずつ提示して1/2mと2/4mがどちらが長いかについて考えさせます。興味関心を高めるだけでなく、分数の第一義のイメージを引き出すことができます。 参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小4算数 複合図形の提示
面積の教材です。複合図形の提示について、子どもの興味を引いたり長方形へのイメージを高めたりすることができます。次の項では、子どものイラストをクリックすると、等積変形や倍積変形など5つの方法について提示することができるように設定しています。広田小の金野先生の実践を参考にしました。 参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小3算数 読めるかな?書けるかな?
大きな数の教材です。10000より大きな数について、読み方や書き方を練習させるために作りました。児童にボタンをクリックさせ、スロットマシンの数字が決めることができます。児童自身で難しい問題にする姿を引き出すことができます。99999999まで扱えます。
小4算数 どう見たのかな?
式を読む教材です。正方形に並んだ丸の数をどう数えたか考えさせる教材です。4×4、5×4-4、5×5-3×3についてどのように見たか考えさせます。線で囲んだり、丸に色をつけたりすることができます。式カードを少しずつ提示することができるようにしたので、部分ごとにどのように見たかを考えさせることもできます。細水先生の教材をスクプレ化したものです。 参照https://drive.google.com/file/d/0B-u7WOIlXmv9TmhvY2pxWnZFVEk/view?usp=sharing
小4算数 2つの正方形を合わせた面積は?
「面積」の発展教材です。一見、辺の長さが分からない正方形2つの面積を求めます。正方形の長さを置き換えて考えるとぱっと解ける楽しさがある教材です。ヒント用の頁を設定しまいます。 Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます https://jamboard.google.com/d/1kDX3KxcLRnGhjbwS-arTX49FbmGhrumobntv4rTIf7s/edit?usp=sharing
小5算数 まわりの長さが同じ長方形と平行四辺形
平行四辺形の面積の導入教材です。周りの長さを変えないで、長方形から平行四辺形に少しずつ変化する様子を提示することができます。「周りの長さが同じだと面積は同じ」という思い込みから問いを引き出すことができます。 Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます) https://jamboard.google.com/d/1hVUflvlk6_JttFGJHKR4DruPv1nS4koRz8UjPO72IMo/edit?usp=drive_link