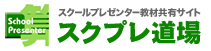サービス終了のお知らせ
新着の教材 新しくアップロードされた教材です
小3算数 23×12の筆算
23×12の筆算の手順を図解した教材です。筆算の順番が分かるよう4コマ漫画の手法を取り入れています。自動に繰り返すこともできるので、そのまま提示して机間指導することもできます。
小4算数 運動会の並び方
いろいろな見方で、式が変わる教材です。例えば、3×4であれば、半径に並んでいる子たちをグループとして見る求め方となり、4×3であれば、円周に並んでいる子たちをグループとして見る求め方です。式をよむ活動が楽しくできます。なお、子どもたちは移動可能です。また、求め方が比べられるページもあります。 Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます) https://jamboard.google.com/d/1i12rdqalJhhM4A_54TIaXiDmLAwngUcKvMn0Vwmukrc/edit?usp=share_link
小3算数 仲良く輪投げするには
円の学習の導入教材です。実際に輪投げをするのは難しいので、スクプレで分かりやすく提示します。「けんなにならないようにするには」という発問によって、ターゲットから等しい距離で投げるという声を引き出します。動物たちは動かすことができます。また、ターゲットから円も描くことができます。参照http://blogs.yahoo.co.jp/jyugyoken/62295534.html
小2算数 オレンジと黄色はいくつ
この教材は、100までの数表を使ったきまり発見の教材です。ウサギやトラ、ネズミをクリックすると、十の位と一の位が入れ替わった数が見つかります。ペンギンはほかにもあるかもと考え始めた時に使う半透明なものです。高学年であれば、成り立つ理由について考えることもできます。
小4算数 立方体や直方体(面・辺・頂点の数)
立方体や直方体の面・辺・頂点の数を数える教材です。空間的な提示をすることで、いくつあるか理解させることに役立ちます。ペンギンをクリックすると面が飛び出す点も、実物ではできないので、子どもたちのイメージを高めます。Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます)もあります。 https://jamboard.google.com/d/1i2IgxvT0jFRLCa7UVehQRVwAkHWk9wI-bSSXZ6OwdbQ/edit?usp=sharing
小4算数 1平方センチメートルを作ろう
面積の教材です。いろいろな図形を分割して、1平方センチメートルになるようにします。図形ははさみを使って分割します。印刷機能を使って、これと同じものを配布すれば、より授業で使いやすいです。 Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます) https://jamboard.google.com/d/1Wi2CD2szBtlzHfY7LQvsksO5zWIctUMlatBWuGr6iC0/edit?usp=sharing
小6算数 回転させた半円
円の面積の活用問題です。図のアとイを合わせた面積を求めます。問題の状況が分かりやすいように、作図する手順で提示できます。イとウが同じ面積になるところがこの教材の面白さです。Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます)もあります。 https://jamboard.google.com/d/1x87aQYRgdyGmSvhBRVyEtM-OcYELlcphlhiTt8PHXFU/edit?usp=sharing
小6算数 同じ形はどれ?
拡大図と縮図の教材です。一見、どれも同じ形に見えますが、重ねたり、マス目を使って辺の長さを数えたりすると、灰色の三角形が違うことがわかります。マス目は星を押すと提示できるようになっています。また、反転は左側のスイッチを使います。 Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます) https://jamboard.google.com/d/1TAsyuf4QAY2IhvoybWeWknuK-Y2lDN8y5xmI8tNA-N0/edit?usp=drive_link
小5算数 12番目は
倍数・約数と素数の教材です。番号をクリックすると、図形が表示されます。6番目まで表示させ、12番目を考えることによって、いろいろな数がかけ算の形で表せることに気付くことができます。表示された図形は、移動することが可能です。坪田耕三先生の実践をスクプレ化したものです。Jamboardのワークシート(Googleにログインしコピーすると使えます)もあります。 https://jamboard.google.com/d/1dWfIvnlB36FY6SuxoAlfj6d3_c5Vbw1iNChnn1mk4dY/edit?usp=sharing